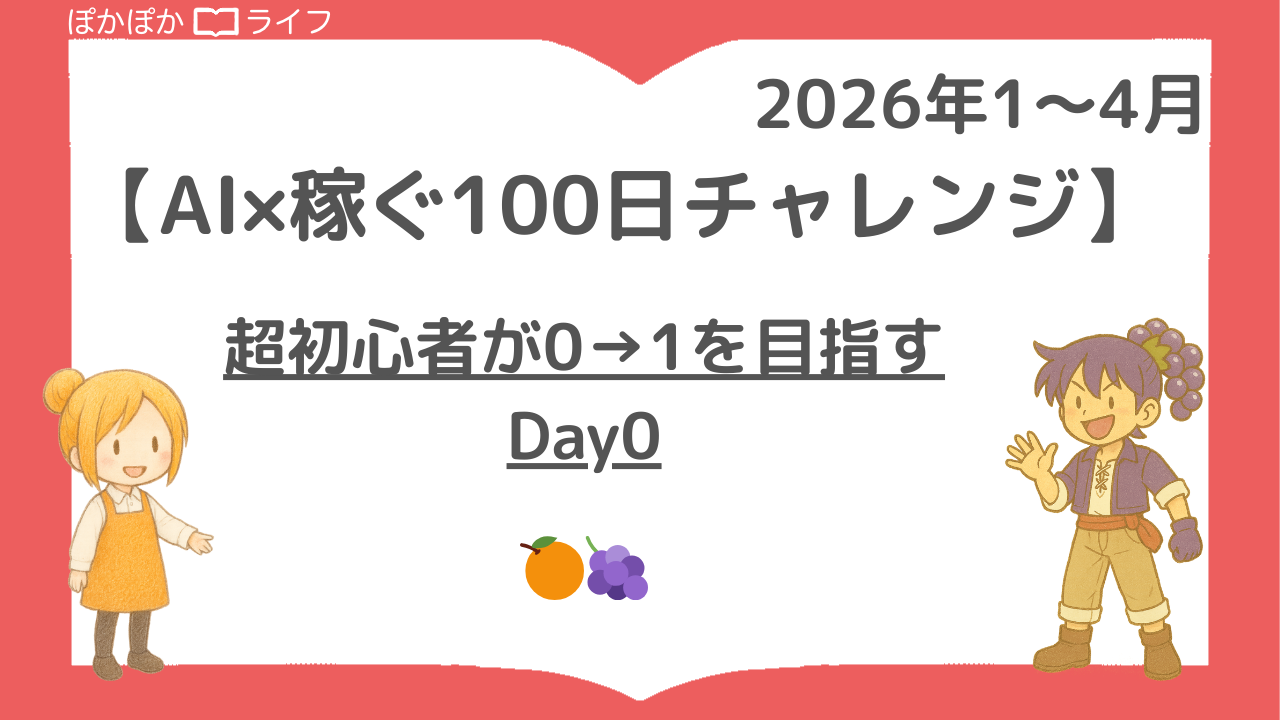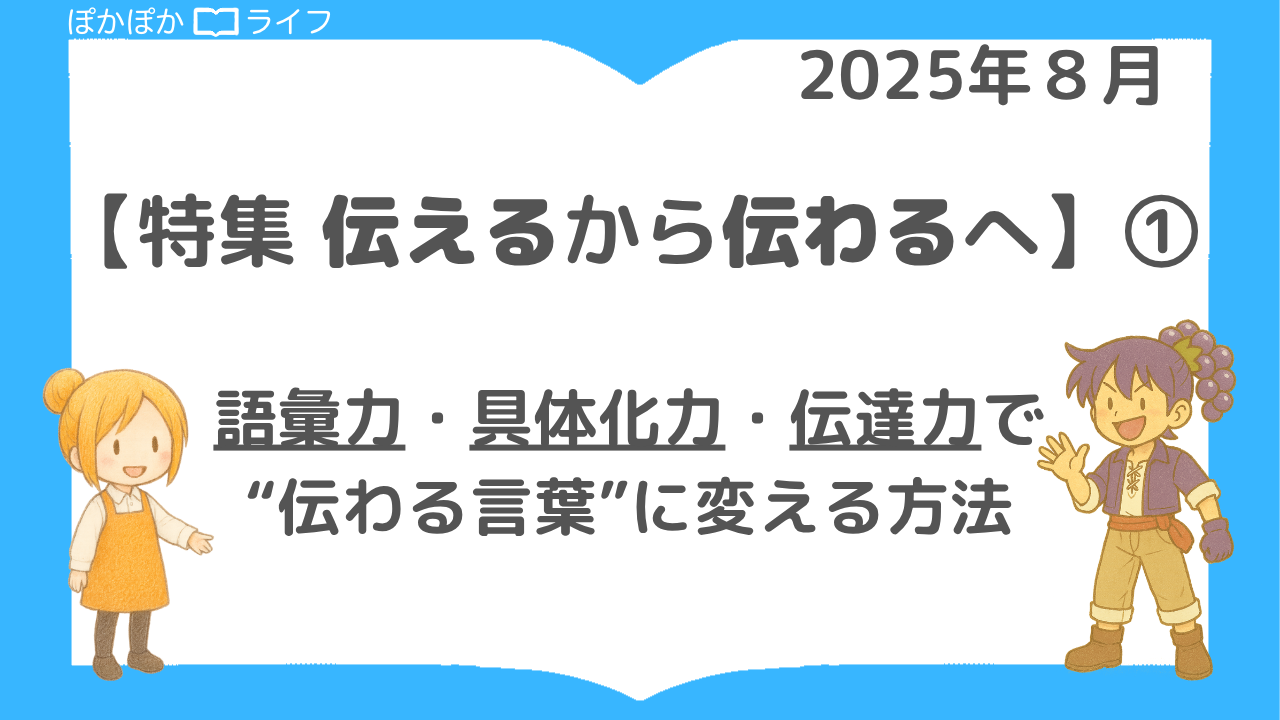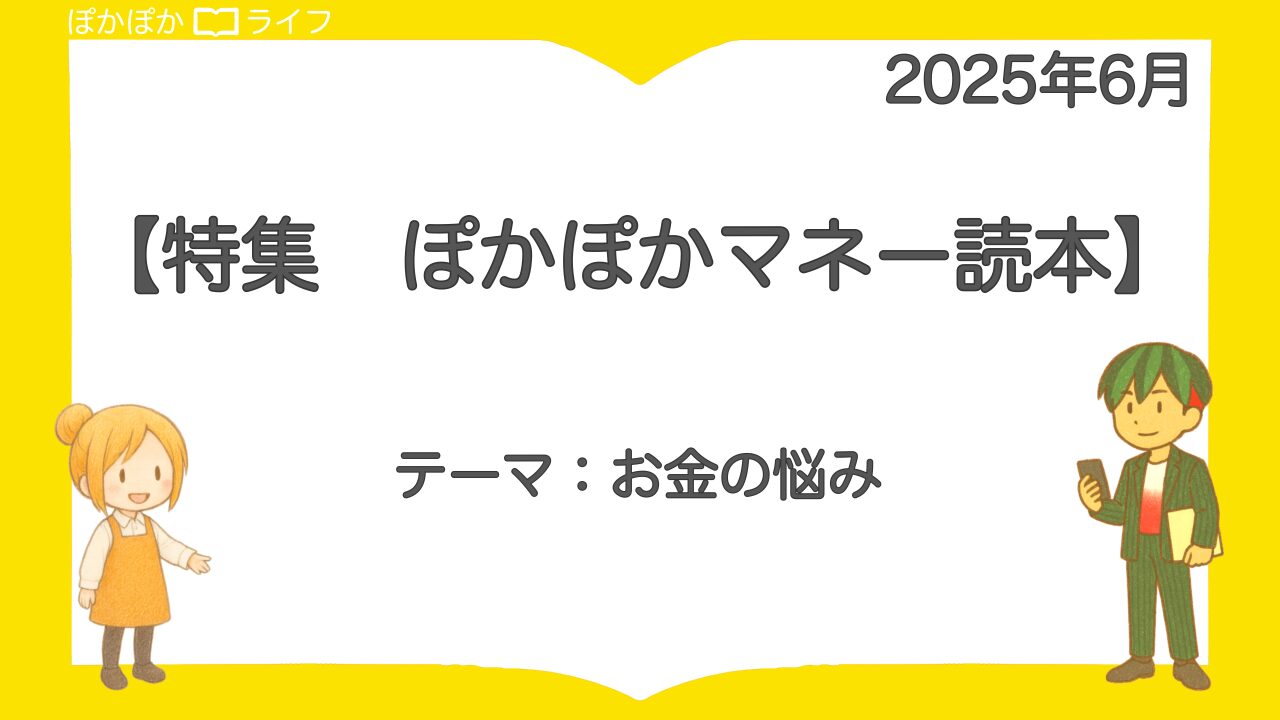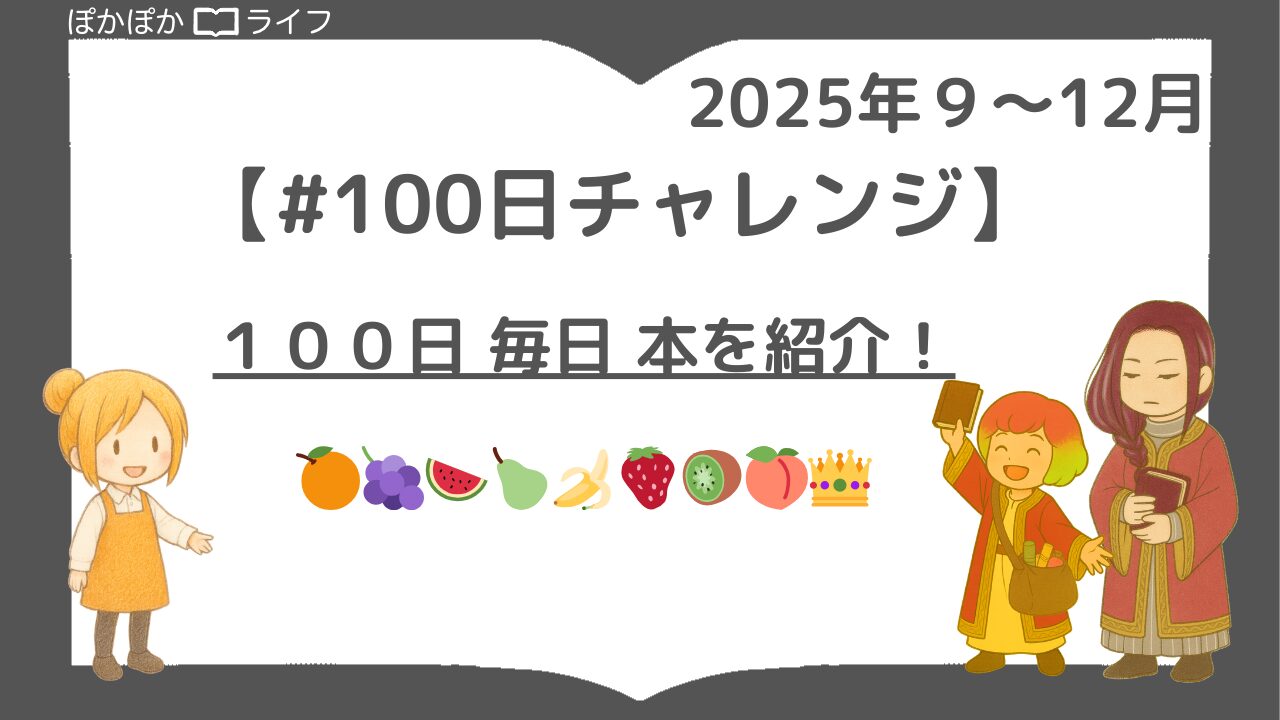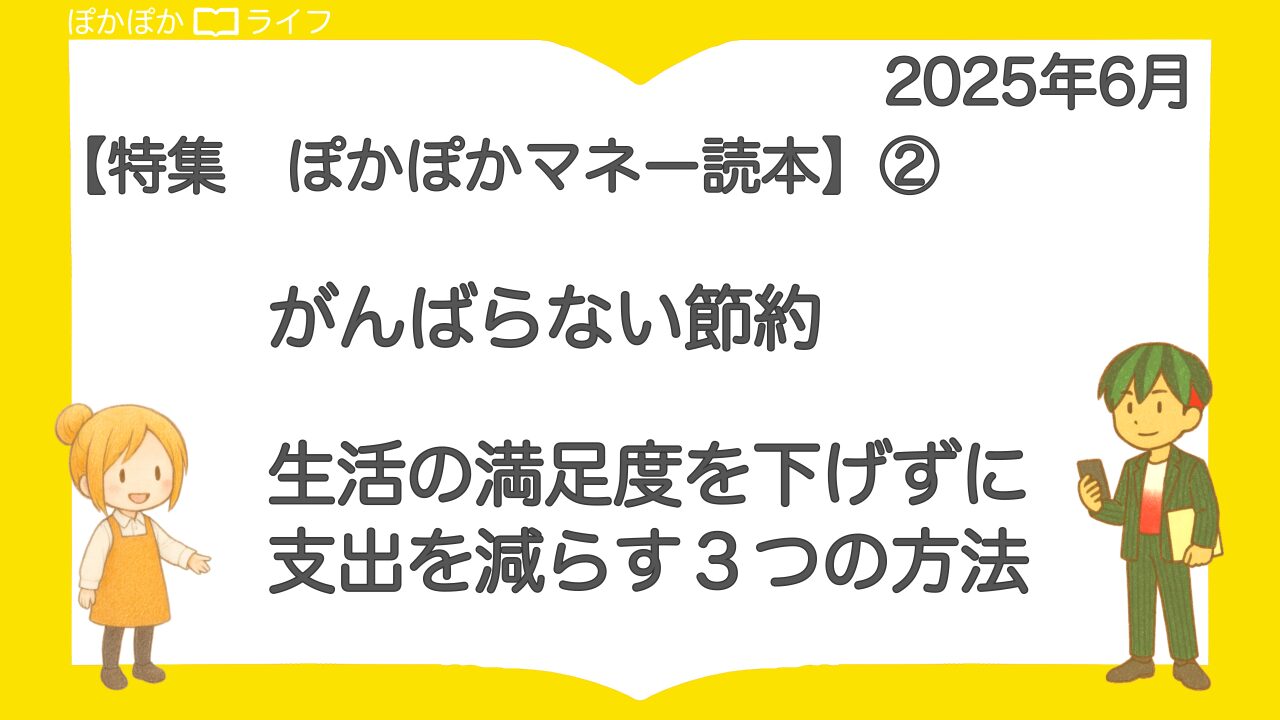【伝えるから伝わるへ】② 『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』に学ぶ!相手を惹きつける話し方と3つの罠回避法
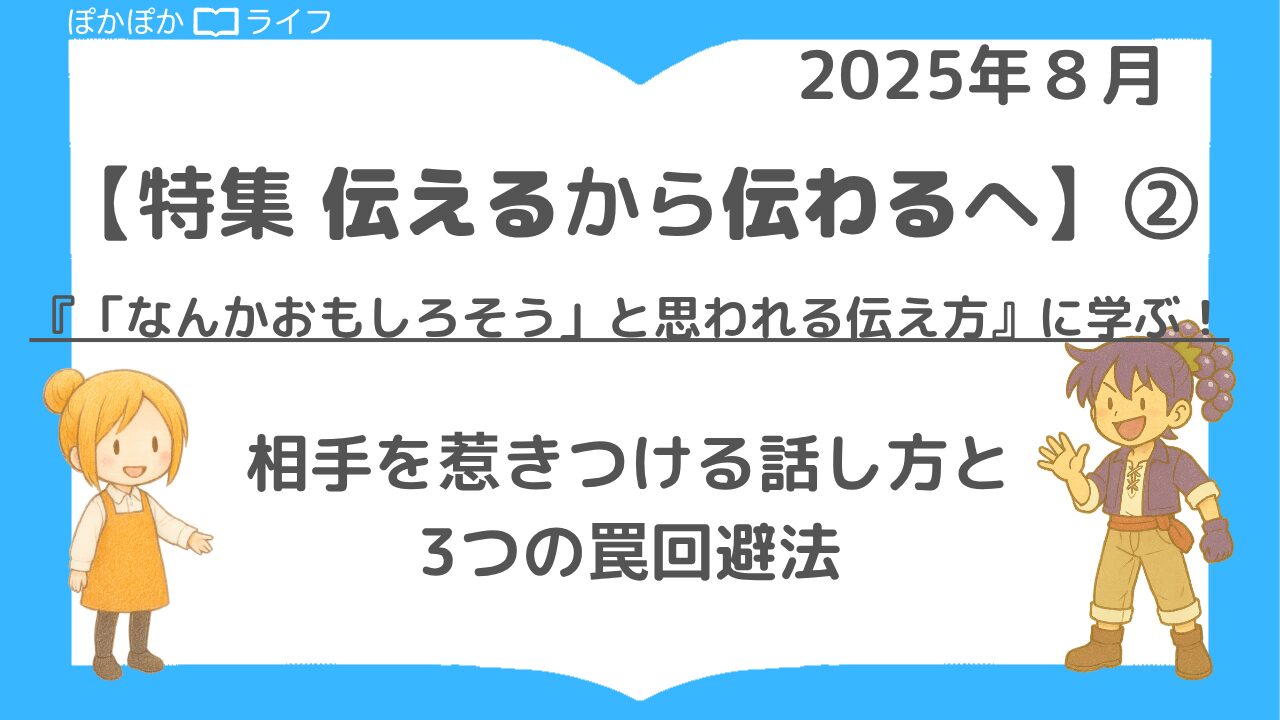
※この記事にはアフィリエイトリンクを含みます
▼8月特集紹介▼
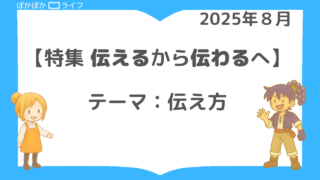
伝え方には罠がある?!
前回の本を実践して、スカイくんに「話が具体的になった」と褒められた!

すぐにやってみる姿勢が素晴らしいです。

こうなると、次に進みたくなるものだな。
今度は魅力的な伝え方を学んでみたい!

一生懸命話しても、反応が薄いというか、思ってた反応が返ってこなくて…。
伝わるだけではなく、惹きつけるような話をしてみたいんだ!

なるほど。
それでは今回は『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』はいかがでしょう?

おお!
本のタイトルが、まさに「なんかおもしろそう」だな!

ふふ、よかったです。
この本では、気づかないうちにやってしまう“伝わらない原因”を、わかりやすい例とユニークな名前で紹介しています。
「見切り発車」や「そんなもん太郎」など、思わずクスッとする事例もありますよ。

うむ!
「罠」を見極めて、思った通りに伝えられるようになってみせよう!

放送作家歴25年で気づいた「22個の罠」
一生懸命話しているのに、相手の反応が薄い。
「ちゃんと伝わっているはずなのに、興味を持ってもらえない…」
そんなもどかしさを感じたことはありませんか。
今回ご紹介する『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』は、放送作家・関圭一朗さんが25年の現場経験からまとめた、「相手が思わず振り向く伝え方」のコツを学べる一冊です。
本書では、気づかないうちにやってしまう“伝わらない原因”を、22の「罠」としてわかりやすく紹介しています。名前も「無個性症候群」「ものさし錯誤」などユニークで、思わず自分もやっていないかドキッとさせられます。
この記事では、その中から特に日常にもビジネスにも役立つ3つの「罠」をピックアップ。
自分の話がもっと惹きつけられるようになるためのヒントをお届けします。
紹介する本『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』
『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』関圭一郎著, サンマーク出版, 2025
こんな人におすすめ
- 話しても、相手が興味を持ってくれない
- つい情報を詰め込みすぎてしまう
- フォーマットや型に頼りすぎる
- プレゼン・スピーチ・日常会話などで、もっと惹きつける伝え方を身につけたい
- 伝え方のクセや失敗パターンを知って、改善のヒントを得たい
気づかぬうちにハマる罠
本書で紹介されている22の「罠」は、どれも気づかないうちにハマってしまうものばかり。
自分ではしっかり伝えているつもりでも、実は相手の興味をそいでしまっていることがあります。
ここではその中から、3つの罠——「見切り発車」「認知不可」「無個性症候群」を取り上げます。
一つずつ見ていきながら、「どう避けるか」のヒントもあわせてご紹介します。
罠No.1:見切り発車
著者はこの見切り発車を、「最初の“罠”が最大の“罠”」として挙げています。
「最初」ってどこ?
タイトルや話し出しの一言――ではありません。
最初=話し出す前の段階。
つまり、話の“方向性”を定めるところです。ここが曖昧なまま走り出すと、伝わり方がぶれます。
それでは、なぜ方向性が重要なのかを具体的に見ていきましょう。
見切り発車を防ぐ3つのポイント
「見切り発車」を防ぐには、伝える前に次の3つを決めておくことが大切です。
- 伝えたいことは何か
― 話の軸を作ります。 - どのように伝えるか
― どんな切り口で、どの部分を使うのかを決めます。 - それは相手にとって伝えてほしいことなのか
― 聞き手にとって必要な情報かどうかを考えます。
例:最高のにんじん
伝えたいのは、農家さんが20年かけて工夫をこらした「最高のにんじん」
単に「このにんじん最高!」と言っても、相手には魅力が伝わりません。
③の「相手にとって伝えてほしいこと」は、人によって違うからです。
- 健康志向の人 → 無農薬で体に良い
- にんじんが苦手な人 → 甘くて食べやすい
- 食にこだわりのない人 → そもそもにんじん情報は不要
誰を想定するかによって、何をどう伝えるか、その後どうなってほしいかまで変わります。
話す前にこの3点を押さえておくことで、「見切り発車」の罠を避けられます。
ポンヌくんならば、どんなことを伝えてほしいだろうか。

私の場合は「最高のにんじん」を作るために、農家さんがどんな苦労をされたのか、どうやって乗り越えてきたのかを知りたいです。

にんじんそのものでもなかった…!

罠No.15:認知負荷
一度に多くの情報を与えられると、人はストレスを感じます。
たとえば、次のような文章を読んでみてください。
文章作成においては、情報伝達の効率性および受け手の理解促進を最大化するために、適切な語彙選択と文脈的整合性を確保しつつ、冗長性の回避および論理的整合性の担保を行い、さらに文意の一貫性を維持しながら読解負荷を低減させる構造的最適化を同時並行的に実施することが重要であると考えられます。
どうですか? 読むのをやめたくなりませんでしたか?
どんなに素材が良くても、情報を一気に押しつけてしまっては、相手は「もういいや」となってしまいます。
伝えたいことが山ほどあっても、情報の洪水で相手を溺れさせてしまっては本末転倒です。
伝えたいことがたくさんあるときは?
そんなときは、途中で立ち止まること。
「どうですか?」や「ここまでで質問ありますか?」など、声をかけて相手に考える時間・受け止める時間を作ります。
小分けにして伝えることで、相手の頭の中で整理されやすくなり、結果的に最後まで聞いてもらえる確率が上がります。
情報は多ければ多いほどいいと思っていた…!

人によって一度に受け止められる量が違います。相手に一番伝わりやすいスピードを心がけたいですね。

罠No.19:無個性症候群
「型」を意識するあまり、あなたらしさやオリジナリティがなくなってしまうことがあります。
これが「無個性症候群」の罠です。
著者は、この罠を避けるためのヒントとして
3つの「あ○○るのを、やめましょう」
を紹介しています。
さて、この○に入る言葉、わかりますか?
ちょっと考えてみましょう。
・
・
・
自分なりの回答は出ましたか?
正解はこちら
- あてはめる のを、やめましょう
- ありふれる のを、やめましょう
- あきらめる のを、やめましょう
では、それぞれの意味を見ていきましょう。
① あてはめるのを、やめましょう
構成を作る際、フォーマットに当てはめるだけになっていませんか?
起承転結や結論ファーストは有効な型ですが、状況によっては逆効果です。
例えば怪談話を「正体は○○だった。はじまりは…」と結論から始めてしまったら、聞き手は興ざめしてしまいます。
② ありふれるのを、やめましょう
どこかで見たことがある表現だと思ったら要注意。
例えば「東京ドーム○○個分」という例えがありますが、東京ドームに行ったことがない人にはピンときません。
もちろん、その表現が一番わかりやすければOKですが、安易に使うと個性が薄れてしまいます。
③ あきらめるのを、やめましょう
伝えるのをやめる理由が「誰かを傷つけるから」なら、それは正しい判断です。
しかし「伝わらないと思うから」という理由なら、あきらめないで工夫して伝えてみましょう。
少し不格好でも、それがあなたの個性になることがあります。
あなたらしさ
伝統の型やよく使われるフォーマットは有効ですが、本当に伝えたいことに合っているかどうかを確認することが大切です。
「型」や「正解」に縛られすぎず、あなたらしい伝え方を磨いていきましょう。
俺の体重は🍇ぶどう120個分だ!

個性的ですが、何キロなのかさっぱりわかりません!

おわりに
「おもしろそう」と思ってもらうには、様々な工夫がいるんだな!
こんな罠が22個もあるとは…!

私も全部読ませてもらいましたが、罠を回避できているとはまだ言えなくて……。
でも少しずつ、意識していこうと思っています。

うむ!そうだな!
まずはどんな罠があるのか。そして罠に引っかからないためにはどうすればいいのか。
それらを知ることが大切だ!

はい!
本の魅力を伝えるためにも、身につけていきたいです。

「おもしろそう」と思われる伝え方
ここまで読んでいただいてありがとうございました!
「見切り発車」「認知負荷」「無個性症候群」
今回ご紹介した3つの罠は、日常の中でつい陥りがちなものばかりです。
話し出す前に方向性を定めることで、聞き手を迷子にさせない。
情報は一度に詰め込みすぎず、相手が受け止められる量とスピードを意識する。
型やフォーマットに頼りすぎず、自分らしい表現を大切にする。
この3つを意識するだけでも、「なんだか伝わらない」を大きく減らすことができます。
そして、「もっと惹きつける話し方を身につけたい」と思った時点で、あなたの伝え方はすでに変わり始めています。
小さな工夫と意識の積み重ねが、相手の心を動かす大きな力になっていくはずです。
本書には、今回紹介できなかった「そんなもん太郎」や「ものさし錯誤」などの19の罠と、その回避方法がまだまだ詰まっています。
気になる方は、ぜひ手に取って「おもしろそう」と思ってもらえる伝え方を磨いてみてください。
必要な本に出会うことで、
あなたの人生が、もっとぽかぽかに温まりますように!
また、次の記事でお会いしましょう🍊

次回予告:「伝え方しだい」で人生は変わる
「相手に影響を与える伝え方って?」そんな疑問を解決。
人間関係を前向きに動かす“伝わる言葉”の磨き方がわかります。
▷8月17日(日)9時公開
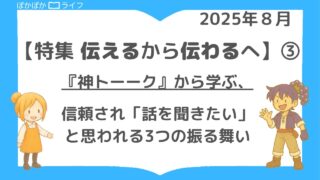
参考文献
『「なんかおもしろそう」と思われる伝え方』関圭一郎著, サンマーク出版, 2025